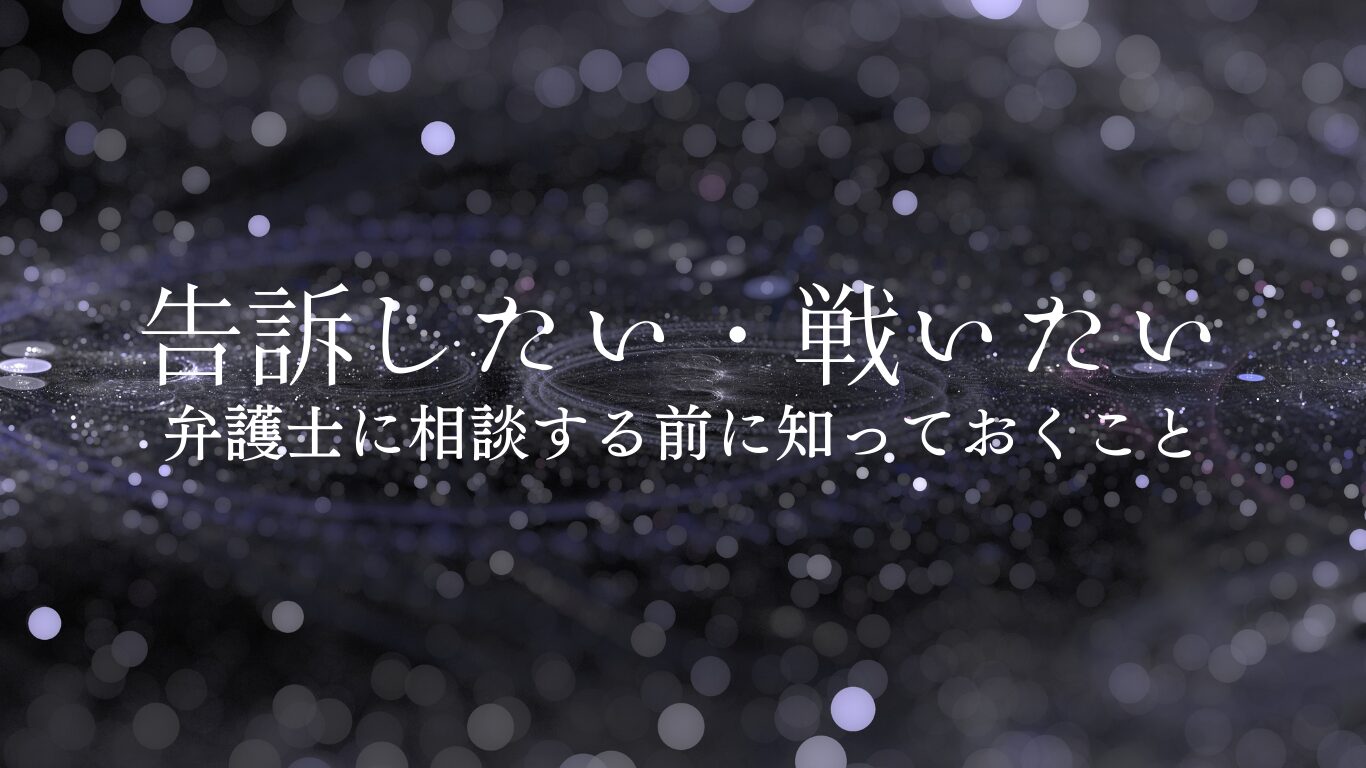「このまま泣き寝入りなんてしたくない」
「詐欺師を許せない。できることなら裁きたい」
「お金は戻らなくても、告訴して記録を残したい」
そう考えるあなたへ――
このページでは、「戦う」という選択肢を検討している方のために、弁護士にできること・できないこと、よくある誤解、そして非弁行為(法律違反)に関する注意点をまとめました。
※このページでは弁護士・調査会社に関する情報を解説していますが、筆者個人としては、被害者が高額な費用を払ってまで利用すべきではないと考えています。
ただし、よくある誤解や実際に相談したい方もいると思いますので、「どんな違いがあるのか」「なぜおすすめしないのか」を正確に説明したうえで、判断材料を提供しています。
どうか、最後までお読みいただき、正しい判断につなげてください。
調査会社・弁護士・警察の違い
| 項目 | 調査会社 | 弁護士 | 警察 |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 被害状況の調査、資金トレース | 法的手続きの代理(告訴状作成、訴訟など) | 犯罪捜査(逮捕・捜索・起訴) |
| 権限・立場 | 民間業者(調査専門) | 国家資格者(法的代理権あり) | 公的機関(捜査権あり) |
| 得意なこと | 資金の流れの可視化、SNS分析など | 書類作成・交渉・民事/刑事手続き | 刑事事件としての立件・捜査 |
| 限界・できないこと | 強制力なし、法的手続きは不可 | 逮捕や捜査はできない | 法的代理や交渉はできない |
| 返金の現実性 | 調査で回収に至るケースは少ない | 勝訴しても回収できない可能性あり | 基本的に返金されない |
| メリット | 自分で調べられない情報が得られる | 法的に主張を通せる | 犯人が逮捕される可能性 |
| デメリット | 悪質業者もあり、費用が高額 | 費用がかかり、結果は不確実 | 動かない、対応に限界がある |
弁護士ができること
弁護士は、法律に基づく手続きや交渉を代理して行える唯一の専門職です。
詐欺被害においては、次のような対応が可能です。
- 弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)を利用し、必要に応じて銀行や関係機関に対して口座名義人や取引履歴の照会を行うことができます
- 詐欺で振り込んだ口座について、口座凍結を要請し、条件が合えば「被害回復分配金」の申請を代理人として行うことが可能です
- 詐欺加害者に対して、代理人として返金を請求することができます
- 必要に応じて、民事訴訟を提起することができます
- 訴訟で勝訴したあとも、詐欺加害者が支払いに応じない場合は、強制執行(差し押さえ)の手続きが可能です
弁護士の強みと、調査会社との違い
特に、最終的な送金先が日本国内の暗号資産取引所(CEX)だった場合は、弁護士が持つ力が非常に有効です。
この場合、一連の法的対応を、すべて弁護士に任せることができます。
また、最近では、調査業務を含めてトータルで対応してくれる弁護士法人も増えています。
被害状況のヒアリングから、ブロックチェーンの資金トレース、法的手続きまですべて一貫して任せられることは、調査会社との決定的な違いです。
調査会社の場合、調査結果をもとに弁護士にバトンタッチする必要があるため、
- 調査会社と弁護士の両方に費用が発生する
- 情報の引き継ぎが二度手間になる
- 弁護士が再度ヒアリング・説明を求める可能性がある
といった課題があります。
これに対し、調査から法的対応まで一貫して対応してくれる弁護士法人であれば、被害者の負担が大幅に軽減され、スムーズな対応が可能です。
「調査の延長線上にある法的手続きまで一貫して任せたい」という方にとって、これは大きなメリットとなります。
弁護士が出来ないこと
弁護士は法的手続きの専門家ですが、すべてを解決できるわけではありません。
特に以下のような点には注意が必要です。
警察ではないため、逮捕や強制捜査はできない
弁護士は民間の法律家であり、刑事事件の捜査権限は持っていません。
加害者を逮捕したり、家宅捜索を行ったりするのは、あくまで警察の仕事です。
ただし、必要な証拠を集めたり、調査したりすることは可能です。
最終ウォレットが海外だった場合は、対応が困難
資金の最終送金先が海外の暗号資産取引所(CEX)や海外個人ウォレットだった場合、
たとえ弁護士に依頼したとしても、できることには限界があります。
たとえば、Binanceに対して「口座凍結や資金照会をしてほしい」と依頼した場合、
Binanceからはこのように返答されます:
「法執行機関(警察)を通じて、Kodex経由で要請してください」
つまり、弁護士経由では対応不可なのです。
Kodex(コデックス)は、日本の仮想通貨関連事業者と警察の間で照会を行うための国内専用の仕組みであり、
海外事業者には直接の拘束力はありません(Binanceなどは任意協力に応じているだけです)。
また、Kodexを利用できるのは警察だけで、弁護士や個人はアクセスできません。
そのため、海外取引所が最終ウォレットだった場合、警察の捜査協力がなければ追跡も凍結も困難になります。
さらに、相手が海外に拠点を持つ個人であった場合、訴訟を起こすには現地の法制度に則る必要があり、
現実的に回収までたどり着くことは極めて困難です。
示談交渉にも応じない可能性がある
「裁判で勝てばお金が返ってくる」と思われがちですが、詐欺事件では訴訟しても実際に返金される割合は非常に低いのが現実です。
判決に勝っても、相手に資産がなければ執行できませんし、海外の加害者が相手なら裁判そのものが不可能なこともあります。
一方で、「示談」は現実的な返金手段として機能する場合があります。
なぜなら、詐欺罪は非常に重く、初犯でも実刑判決が下されやすいからです。懲役刑しかなく、執行猶予がつかなければすぐに刑務所行きとなる可能性があります。
そのため、前科や実刑を避けたい加害者は、起訴される前に示談を成立させようとする傾向があります。
刑事処分を軽くするための“交渉材料”として、返金(示談金)に応じる可能性があるのです。
ただし、相手が海外にいたり、連絡が取れなかったり、話し合いに応じない場合は、示談交渉がそもそも成立しないこともあります。
「弁護士が間に入れば返ってくる」というのは理想論であり、現実には交渉のスタートラインにすら立てないことも少なくありません。
勝訴しても、支払い能力がなければ返金されない
たとえ裁判で勝っても、加害者に財産がなければ強制執行も意味をなしません。
支払い義務を法的に確定させられても、現実にお金が返ってくるとは限らないのが詐欺事件の難しさです。
弁護士に相談する前に知っておきたいこと
※この記事は、東京弁護士会「非弁提携弁護士対策本部」の注意喚起文をもとに、当サイトで再構成・解説したものです。原文はこちらをご覧ください。
国際ロマンス詐欺のような被害は、詐欺そのものの損失だけでなく、「被害を取り戻そう」とする過程で再び損害を被るという、いわゆる二次被害も深刻です。
特に、非弁業者(弁護士資格を持たない者)と連携している弁護士に依頼してしまったことで、以下のような被害が報告されています。
こんな広告や対応には要注意!
- たった1人の弁護士事務所なのに「24時間365日対応」と謳っている
- 「国際ロマンス詐欺専門」などと表現しているが、実際には経験が乏しい
- 高額回収事例を掲げているが、その詐欺が同種とは限らない
- LINEでのやりとりや電話相談の中で、実は弁護士が出てこない
- 委任契約も電話と電子署名で完結し、事務所にも行っていない
これらは「非弁業者との提携」や「大量案件処理の温床」となりやすく、
高額の着手金を支払ったのに進捗報告もなく、結局“着手金倒れ”だったという苦情が各地の弁護士会に寄せられています。
被害を避けるためのチェックポイント
- 弁護士本人と直接会って説明を受ける(可能であれば事務所訪問)
- 契約書は紙ベースで署名・押印(一度持ち帰って検討)
- 着手金とリターンの見込みのバランスを冷静に考える
- 「専門」「特化」といった言葉に惑わされない
- 日本弁護士連合会の弁護士情報検索で事務所・登録情報を確認する
👉 https://www.bengoshikai.jp/
📝 引用元:
この内容は、東京弁護士会「非弁提携弁護士対策本部」の注意喚起に基づいています:
👉 国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点|東京弁護士会
非弁行為をわかりやすく説明します
たとえば、あなたが「国際ロマンス詐欺 返金 弁護士」などのキーワードでネット検索して、ある法律事務所のホームページを見つけたとします。
- 「まずは無料相談をご利用ください」
- 「一次調査無料」
- 「LINEで24時間対応」
無料なら…。弁護士なら…。そう思ってLINEで相談を始めたとしましょう。
でも、そのやりとり、実際に返事をくれているのは誰でしょうか?
その事務所には弁護士が1人しかいないはずなのに、LINEの返信は早く、対応も丁寧。
「ご担当の方はどなたですか?」と聞いてみたら、
「事務員の○○です」と返ってきた——。
それだけなら問題ではありません。
ですが、弁護士と一度も会話していないのに「契約書を交わしましょう」と言われたら、注意してください。
このようなケースでは、非弁提携(弁護士資格を持たない業者と弁護士が手を組む行為)である可能性があります。
調査報告書を弁護士が出していない?
中には、調査も請け負ってくれるという法律事務所があります。
ですが、その「調査」は弁護士がやっているわけではなく、外注された調査会社が行っていることもあります。
たとえば、
- 調査会社が調査
- 法律事務所名で契約書を交わす
- 調査報告書も事務員から送られてくる
- 弁護士とは一度も会っていない・話していない
これが、非弁行為とみなされるケースです。
高額な着手金、本当に払う価値がありますか?
調査の結果、
「最終ウォレットは海外でした。ここから先は警察にご相談ください」と言われたら、
高額な着手金を払った意味があったでしょうか?
それなら最初から調査会社に依頼しても、同じ結果だったのでは…?
ポイント
調査報告が出されるなら、誰が調査したのかを確認する
弁護士と直接話をするまでは契約しない
契約内容は必ず紙で確認する(電子契約は慎重に)
弁護士の「名義貸し」という事件も【実例紹介】
国際ロマンス詐欺や暗号資産詐欺の被害者に対して、「全額返金可能」「スピード対応」などとうたい、着手金を集めていた弁護士らが実際には対応せず、事務員や広告会社に丸投げしていたという事件が、NHKによって報じられました。
🔗 NHKニュース(2025年5月14日):
詐欺の“二次被害” 弁護士たちが陥った「着手金ビジネス」の闇
この事件では、
- 弁護士が広告会社の言いなりになって名義を貸し
- 事務員が契約や対応を担当
- 集められた30億円のうち22億円以上が広告会社に流れていた
という実態が明らかになっています。
これは非弁行為そのものとは少し違いますが、「弁護士が名義だけを貸し、実際の業務は広告会社や事務員に任せ、自らはほとんど関与せずに報酬を得ていた」という構造で、被害者にとっては非常に悪質です。
このような事件が実際に起きていることを知っておくことは、二次被害を防ぐ上でもとても重要です。
非弁行為にあった場合の連絡先
- 日弁連の相談窓口(日弁連:市民相談窓口一覧)
まとめ
法律の力で“戦う”という選択は、とても勇気のいることです。
でも、その道の途中で、また新たな被害に遭ってしまうことだけは、どうか避けてください。
被害者であれば、「返金の可能性があるなら依頼したい」と思うのは当然です。
可能性は、ゼロではありません。でも、限りなく低いです。
そこを理解したうえで、調査会社や弁護士に依頼するかを判断してください。
ここまで解説してきましたが、私自身は、どちらにも安易に依頼することをおすすめしません。
(あくまで私個人の意見です。依頼する人を否定するつもりはありません)
なぜなら、詐欺で大金を奪われた上に、さらに着手金や調査費用まで失うことになるのは、本当に苦しいことだと思うからです。
繰り返しになりますが、まずは一度、警察に相談してみてください。