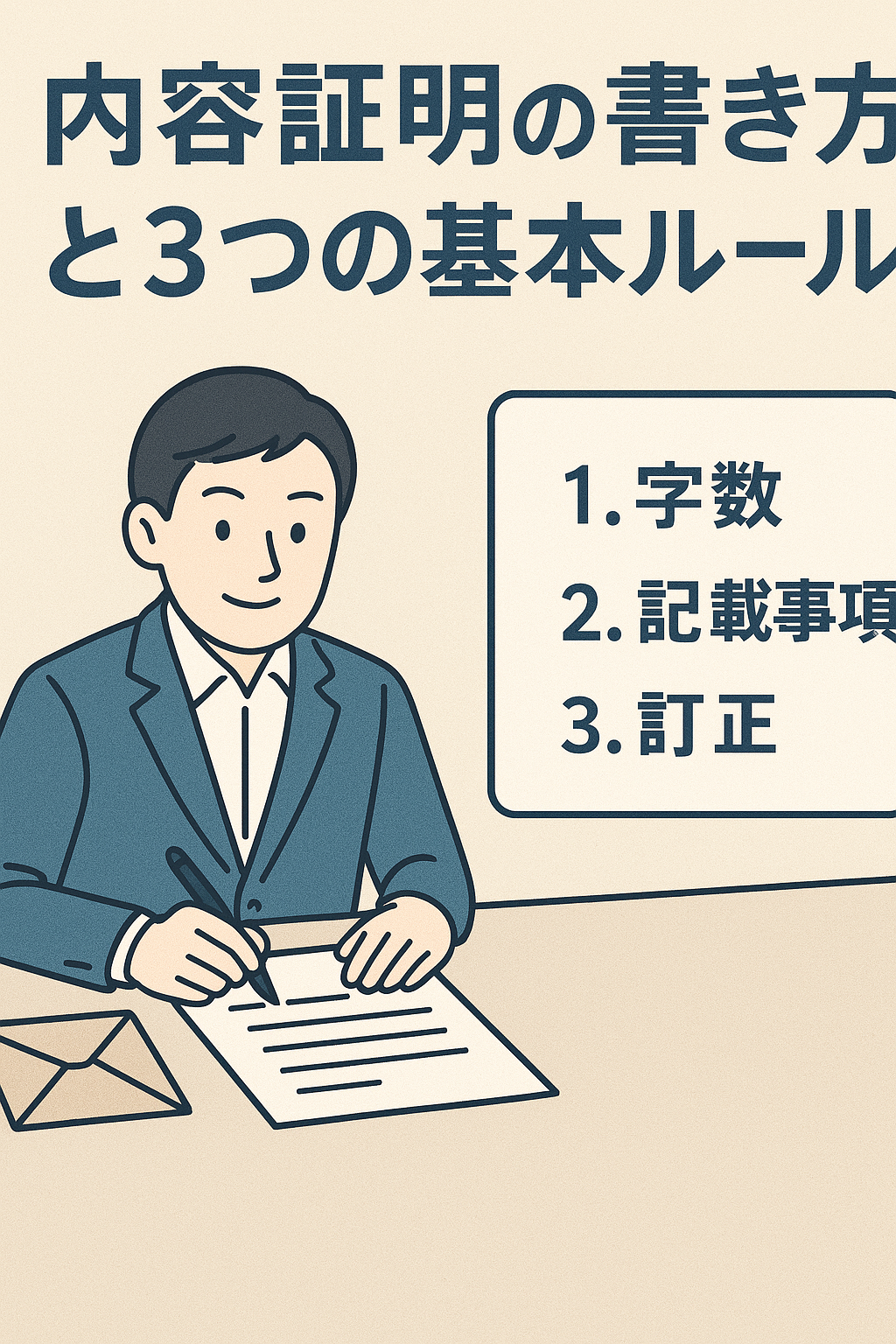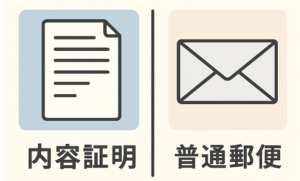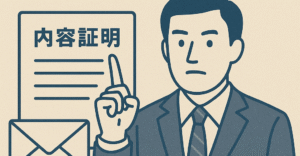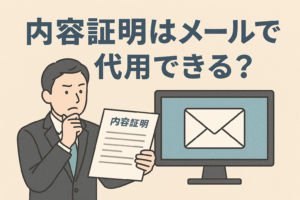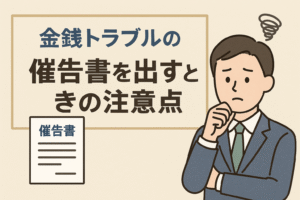内容証明の書き方と3つの基本ルール
内容証明郵便は、相手に対して法的な意思表示をする際に非常に有効な手段です。ですが、書き方にはいくつかのルールがあり、それを守らなければ受付けてもらえないことも。この記事では、内容証明の書き方の基本と、必ず押さえておきたい3つのルールをご紹介します。
1. 文字数と行数の制限
内容証明では、1行20字以内、1枚26行以内という制限があります。これを守らないと形式不備として受け付けられないため、パソコンで作成する際にも文字数と行数に気を配る必要があります。
2. 必要な記載事項
誰が誰に対して、どのような内容を通知するのかが明確でなければなりません。発信人の氏名・住所、受取人の氏名・住所、日付、本文、差出人の署名など、基本的な要素がすべて記載されているか確認しましょう。
3. 訂正は不可
内容証明では、後からの加筆・訂正が一切できません。記載ミスをしてしまうと再提出になる可能性もあるため、事前に十分なチェックが必要です。特に金額や期日などの数字には注意を払うようにしましょう。
内容証明の送付には専門家のサポートも
内容証明は、単なる手紙ではありません。相手に対して「法的な圧力」を与える側面もあるため、慎重な文面構成が求められます。
特に以下のようなケースでは、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 契約解除・債権回収など、トラブルが大きくなりそうな場合
- 一度送ったが無視されたため、再度通知したい場合
- 相手が法人・事業者などで、文書の形式に厳しいケース
専門家に依頼することで、法的観点からのアドバイスを受けながら、適切な表現で確実に意思を伝えることができます。
まとめ
内容証明の作成には、形式と内容の両面での注意が必要です。今回ご紹介した「文字数・記載事項・訂正禁止」という3つのルールをしっかり守ることで、内容証明の効果を最大限に引き出すことができます。
「一人で作るのは不安…」という方は、専門家に相談するのも一つの方法です。当事務所では、初めての方にも安心してご利用いただけるよう、ていねいなサポートを心がけています。
行政書士しまだ法務事務所では、内容証明の文書作成から郵送の流れまで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。