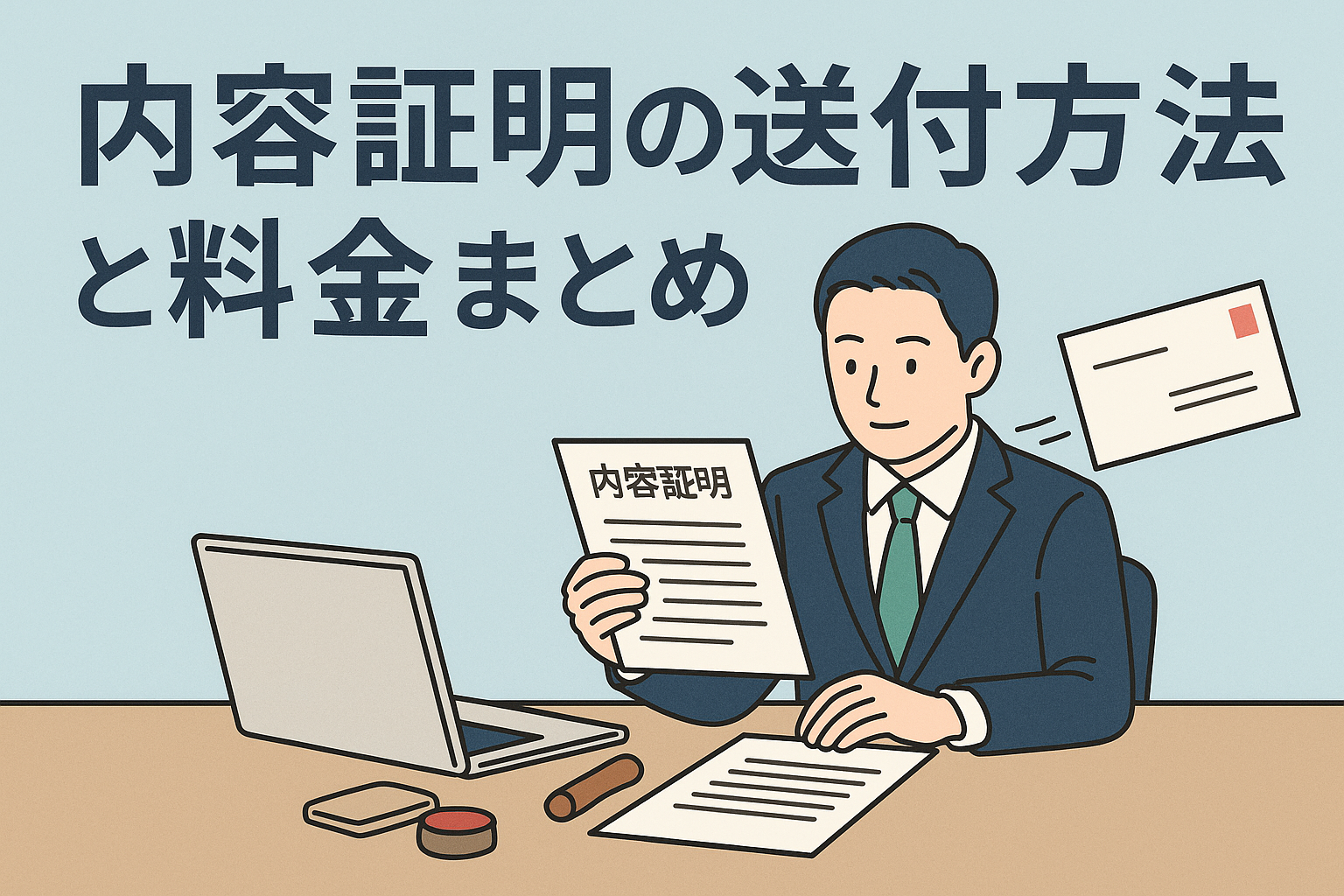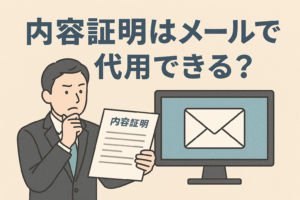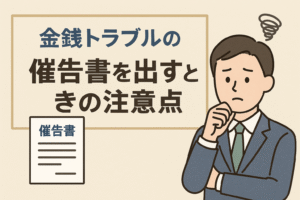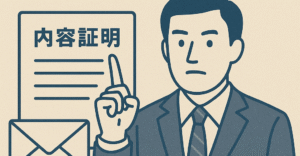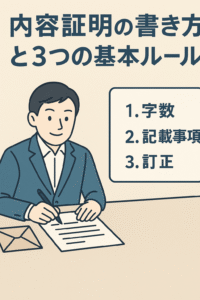内容証明の送付はどうやる?基本の流れを解説
内容証明郵便を使えば、相手に「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明することができます。けれど、いざ自分で送るとなると「どうやって手続きするの?」「どこに行けばいいの?」「料金はいくら?」と疑問も多いはずです。
この記事では、内容証明郵便の送付方法と料金について、初めての方にもわかりやすく解説します。
送付方法1:郵便局で送る(もっとも一般的)
最も基本的な方法は、郵便局の窓口で内容証明を提出する方法です。以下のものを準備して窓口に行きます:
- 同じ内容の文書3通(相手用・郵便局保管用・差出人控え)
- 封筒(宛名のみ記載、封はしない)
- 印鑑(署名でなく押印を求められることがあります)
- 本人確認書類(必要な場合も)
窓口で文書内容の確認と手続きを行い、その場で控えが返却されます。
送付方法2:電子内容証明(ネットで送る)
日本郵便の「電子内容証明郵便サービス」を利用すれば、パソコンから24時間いつでも送付手続きが可能です。郵便局に行く必要がないため、忙しい方や遠方の方にも便利です。
ただし、初回登録には手続きが必要で、利用にはパソコン環境と一定の操作知識が必要になります。また、法人としての登録も可能です。
送付時に選べるオプション
内容証明郵便には、いくつかのオプションサービスがあります:
- 配達証明:相手に届いたことを記録として残す(おすすめ)
- 書留郵便:内容証明自体が特定記録扱いになるため、追加不要
- 速達:早く届けたい場合に追加可能
とくに配達証明は、相手が「受け取っていない」と主張するのを防ぐために重要です。
料金まとめ(2025年時点)
内容証明郵便の料金は、基本料金に加えて、内容証明の手数料や配達証明のオプション料金が加算されます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 定形郵便(25g以内) | 84円 |
| 書留料 | 435円 |
| 内容証明手数料(1枚目) | 440円 |
| 内容証明手数料(2枚目以降) | 260円/枚 |
| 配達証明 | 340円 |
たとえば、1枚の文書+配達証明を送る場合、合計はおよそ1,300円前後になります。
文書作成の注意点
内容証明郵便で送る文書には、次のようなルールがあります:
- 1行20文字以内・1枚26行以内
- 句読点やスペースも1文字としてカウント
- 署名または押印が必要
このルールに違反すると差し戻されることもあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
行政書士に依頼する場合
内容証明は自分で作成・送付することも可能ですが、法的な表現や書式のミスを防ぐために行政書士に依頼するケースも多くあります。
行政書士は、内容のチェックから送付手続きまでトータルで対応できるため、特にトラブルが複雑な場合や法的効果を重視する場合には安心です。
まとめ:内容証明の送付はルールを押さえて正確に
内容証明郵便の送付は一見むずかしく思えますが、手順を理解すれば決して難しくはありません。大切なのは、送付の目的に合った形式・オプションを選び、文書の内容を適切に整えることです。
少しでも不安がある場合は、行政書士に相談することで安心して手続きを進めることができます。
行政書士しまだ法務事務所では、内容証明の文書作成から郵送の流れまで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。