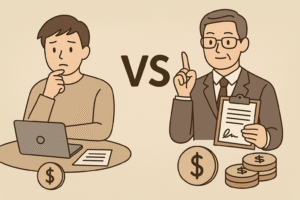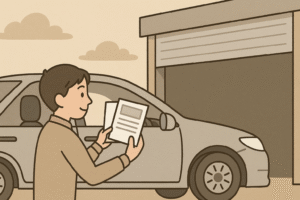宅建業免許取得に欠かせない「事務所要件」とは?
宅建業の免許を取得する際に、見落としやすく、かつ重要なポイントとなるのが「事務所要件」です。免許の審査では、書類上の整合性だけでなく、実際の事務所が業務に適しているかどうかが厳しくチェックされます。
本記事では、宅建業免許における「事務所の基準」について、注意点やNG例を交えて解説します。
事務所として認められるための基本条件
宅建業における事務所とは、単なる住所や物理的スペースではなく、継続的に宅建業を営む拠点としての体制が整っている場所を指します。主な要件は以下のとおりです:
- 机・椅子・電話などの事務設備があること
- 専任の宅建士が常勤可能な状態で勤務できること
- 独立性のある空間であること(他業種との明確な区分)
- 事務所使用の権原(賃貸契約など)が明確であること
これらが整っていないと、書類審査は通っても「現地調査」でNGとなる可能性があります。
レンタルオフィスやシェアオフィスの注意点
最近では、費用を抑えるために「レンタルオフィス」や「シェアオフィス」を利用する方も多く見られますが、これらを宅建業の事務所として使用する場合、特に注意が必要です。
- ブース型(パーテーションで区切られているだけ)のオフィスはNGとなる可能性が高い
- 他業種と受付が共通の場合、独立性が認められないことがある
- 契約形態が「席の利用権」にとどまっている場合、事務所使用権原とみなされないことも
利用を検討しているレンタルオフィスが宅建業に使えるかどうか、事前に管轄の窓口に確認することを強くおすすめします。
自宅兼事務所の場合はどうなる?
「自宅を事務所として使いたい」というケースもありますが、以下の点で審査が厳しくなる傾向にあります:
- 居住空間と業務空間の区分が明確でない
- 事務所スペースが著しく狭く、打ち合わせ等に適さない
- 賃貸住宅の場合、契約上「事業利用不可」になっていることがある
とはいえ、完全にNGというわけではなく、しっかりと間仕切りを設けるなどの対策を取れば、認められるケースもあります。
看板・表示義務にも注意
宅建業者は、免許取得後、事務所の外部に「宅建業者票」や「免許証番号」などの表示を行う義務があります。
事務所が他業種と同居している場合、この表示ができるかどうかも審査対象です。
事務所使用権原の証明も必要
申請時には、事務所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書や登記簿など)の提出が求められます。
使用目的が「住居専用」になっている契約書では、再契約や覚書の取得が必要なこともあります。
まとめ:事務所選びは慎重に
宅建業免許における「事務所要件」は、単なる形式ではなく、業務運営の基盤として非常に重要な要素です。事務所の形態によっては、免許取得が困難になったり、現地調査で差し戻しとなったりするリスクもあります。
行政書士しまだ法務事務所では、宅建業免許申請における事務所要件のチェックから、現地調査対応、使用権原に関する契約書の確認まで、幅広くサポートしています。お気軽にご相談ください。