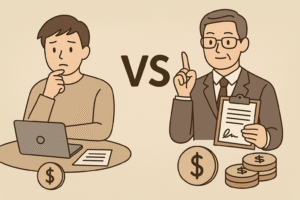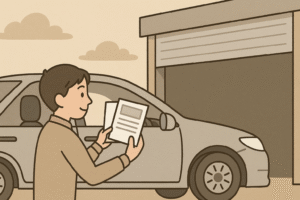宅建業免許には「専任の宅建士」の設置が必須
宅建業(不動産業)を営むには、必ず「専任の宅地建物取引士(以下、宅建士)」を事務所ごとに配置しなければなりません。これは免許取得時だけでなく、営業を続ける限り維持しなければならない法律上の義務です。
しかし「専任」とは何か、どこまでの勤務実態が求められるのか、実は誤解されやすい部分でもあります。本記事では、宅建士の設置義務とその具体的な要件についてわかりやすく解説します。
宅建士の設置義務とは?
宅建業法第31条に基づき、宅建業者は「事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人以上」の割合で宅建士を置く必要があります。
さらに、重要事項の説明・契約書への記名押印などは宅建士のみが行える業務であり、営業実務上も宅建士の設置は不可欠です。
「専任」の意味と勤務条件
専任の宅建士とは、以下の条件をすべて満たす者をいいます:
- その事務所に常勤している(他の会社との兼務不可)
- 宅建業に従事している(名義貸しNG)
- 週30時間以上の勤務実態がある(非常勤不可)
たとえば会社役員が宅建士として登録する場合も、実際に事務所に勤務している必要があります。
よくあるNGパターン
① 他社との兼務
「平日は別の会社で働き、週末だけ宅建士として勤務」は専任として認められません。パートタイムや副業的な位置づけでは不許可となる可能性があります。
② 実態のない勤務
「勤務実態がなく、名義だけ貸している」状態は違法です。行政処分や免許取消の対象にもなり得ます。
③ 専任で登録していた宅建士が退職・不在になったまま放置
専任の宅建士が不在になると、2週間以内に新たな宅建士を補充しなければ違反となります。
必要な書類と提出のタイミング
免許申請時には、以下の書類で宅建士の資格・専任性を証明します:
- 宅建士登録証の写し
- 誓約書(専任性を証明)
- 勤務実態を証明する書類(雇用契約書、給与明細など)
なお、変更や退職があった場合は「変更届出」が必要です。都道府県ごとの書式に沿って、忘れず提出しましょう。
支店・営業所ごとの対応
本店だけでなく、支店・営業所ごとに宅建士の設置義務があります。たとえ少人数であっても、事務所単位で法定人数を満たす必要があります。
宅建士の有資格者を採用するには?
自社に有資格者がいない場合は、新たに採用するか、役員や代表者が資格を取得する必要があります。採用には、以下のようなルートが有効です:
- 不動産系の求人サイト
- ハローワーク
- 行政書士・社労士等のネットワークによる紹介
まとめ:専任性と実態を意識した運用を
宅建業者にとって「専任の宅建士」は、法令遵守と業務運営の要です。「とりあえず名義だけ借りる」「週1回だけ出社」といった対応では、免許が取得できない・取り消されるリスクすらあります。
行政書士しまだ法務事務所では、専任宅建士の設置条件のチェックから、書類作成・要件該当の相談まで丁寧にサポートしております。お気軽にご相談ください。