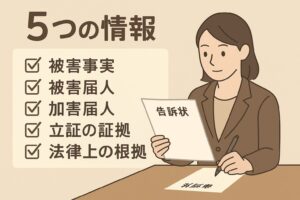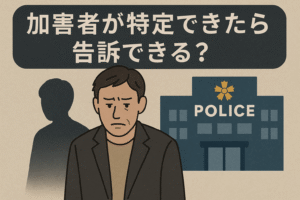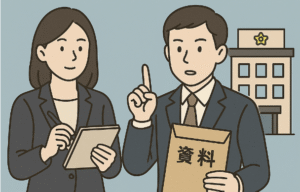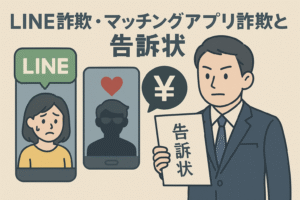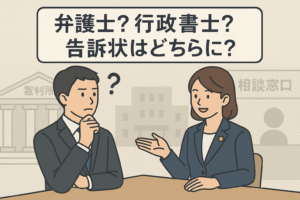「詐欺にあった…でも何から始めればいいの?」
被害を受けたあと、感情的にも混乱しがちですが、告訴状を作成するには一定の準備と流れが必要です。この記事では、詐欺被害にあったときに告訴状を提出するまでの手順を、行政書士の視点から分かりやすくご紹介します。
目次
STEP1:まずは被害状況の整理
告訴状は「法的な文章」です。まずは、自分の被害がどんな経緯で、いつ、誰に、いくらの損害を受けたのかを整理しましょう。ポイントは以下のとおり:
- やり取りの経緯(時系列)
- 相手の情報(名前・SNSアカウントなど)
- 被害額・送金方法・振込先情報など
STEP2:証拠資料の収集
口頭だけでは立証が難しいため、できる限り証拠を集めることが大切です。
- LINEやSNSのやり取り(スクリーンショット)
- 振込明細、仮想通貨の送金履歴
- 詐欺サイトのURL・画面キャプチャ
- 契約書・請求書などの書類
デジタルデータは印刷して提出できるようにしておきましょう。
STEP3:告訴状の下書きを作成
証拠が揃ったら、それをもとに告訴状の下書きを作成します。形式は特に定まっていませんが、一般的には以下のような構成です:
- 宛先(◯◯警察署長 殿)
- 告訴人の情報(氏名・住所・連絡先)
- 被疑者の情報(わかる範囲で)
- 犯罪事実の概要(時系列でまとめる)
- 被害額と証拠資料の説明
- 処罰を求める旨の記載
STEP4:行政書士にチェック・作成依頼も可
告訴状は書類不備があると受理されないことがあります。
行政書士に依頼することで、形式・内容の整った告訴状が作成可能です。
また、証拠の整理や表現の工夫により、警察側の理解も得やすくなります。
STEP5:警察署へ提出
告訴状が完成したら、所轄の警察署(事件地または被害地)に持参します。担当課(生活安全課や刑事課など)で対応されることが多く、受付で「告訴状の提出に来た」と伝えましょう。
その場で受理されるとは限らず、内容確認・聴取を経て後日判断されるケースもあります。
まとめ
- まずは事実を時系列で整理することから始める
- 証拠の保存・印刷も重要な準備のひとつ
- 構成や書き方に不安がある場合は行政書士に相談を
行政書士しまだ法務事務所では、詐欺被害にあった方向けの告訴状作成支援を行っています。お気軽にご相談ください。