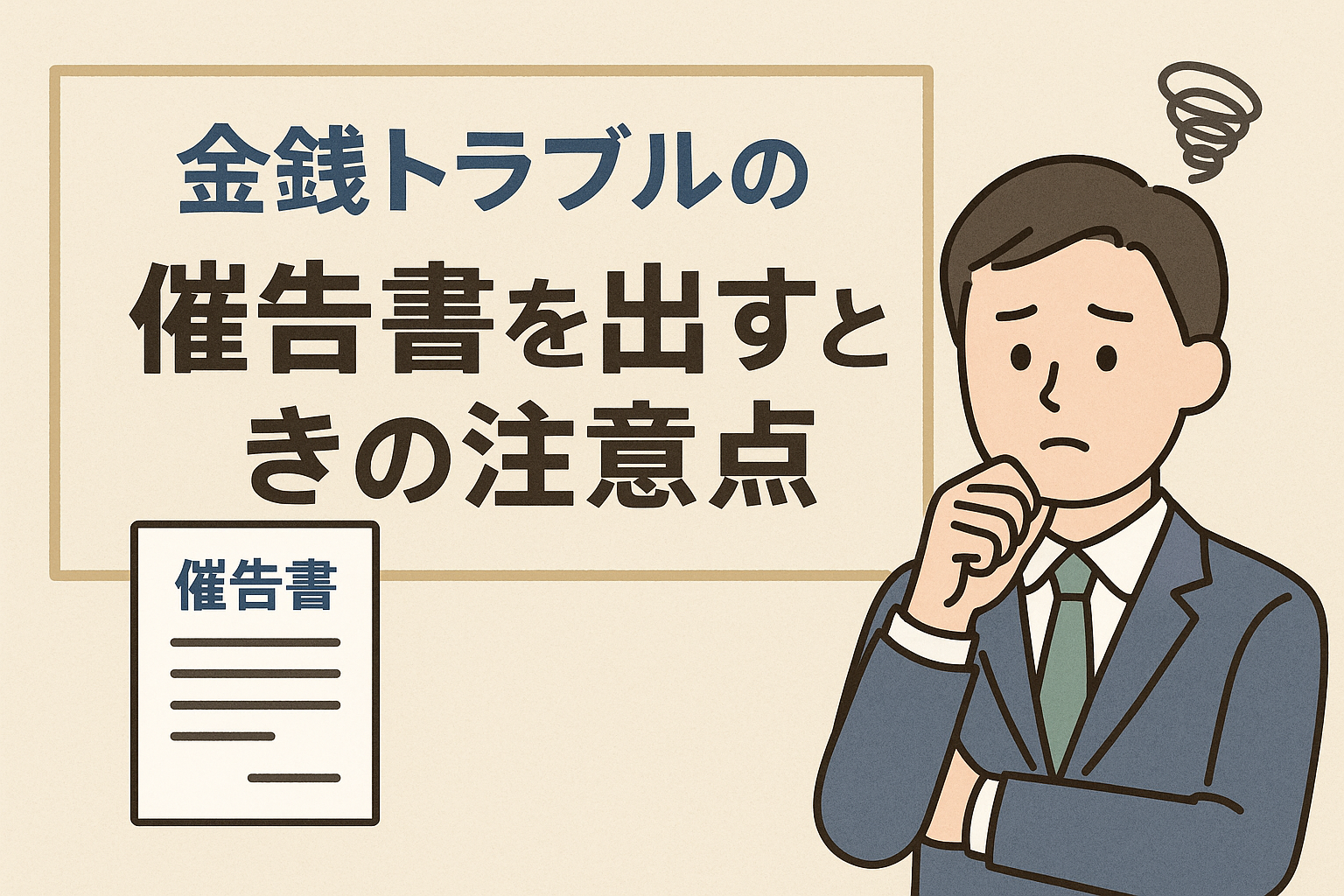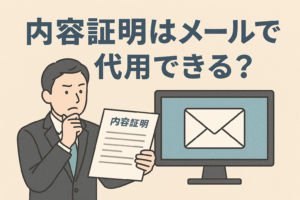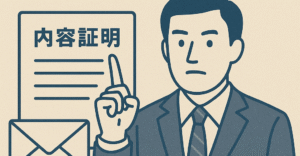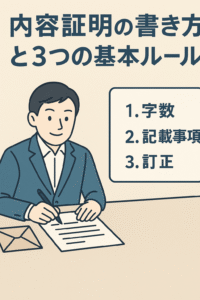催告書とは?金銭トラブルにおける重要な一手
「貸したお金が返ってこない」「支払期日を過ぎても家賃が入ってこない」——金銭トラブルにおいて、まず最初に取るべき法的手段のひとつが「催告書(さいこくしょ)」です。これは、相手に対して正式に支払いを促す文書であり、証拠としての効力も持ちます。
単なる電話やメールでの催促と異なり、内容証明郵便で送付された催告書には、「いつ、どんな内容で請求したか」という記録が残るため、後々のトラブル回避や法的手続きへの布石として非常に有効です。
注意点1:感情的な内容はNG
金銭トラブルは多くの場合、感情が絡むものです。しかし、催告書には怒りや不満をぶつけるような内容を盛り込むべきではありません。冷静かつ事実に基づいた表現が求められます。
たとえば、「いい加減にしてください!」や「誠意を見せろ!」といった主観的な表現は避けましょう。その代わりに、「○年○月○日付で貸与した○万円の返済が未了であるため、下記期日までに返済いただきたく、本書面をもって催告します」といったように、客観的かつ明確に伝えることが大切です。
注意点2:支払い期日は明確に設定する
催告書では、いつまでに、いくらを、どのように支払ってもらいたいかを具体的に示しましょう。たとえば、「本書面受領後7日以内」や「2025年7月10日までに」といった具合に、期限を明示することが重要です。
また、支払い方法(振込口座や現金手渡しなど)についても明記することで、相手の対応をスムーズにし、後の言い逃れを防止できます。
注意点3:証拠としての効力を意識する
催告書を送る目的の一つは、万一、法的措置に発展した場合に備えて証拠を残すことです。そのため、送付には内容証明郵便+配達証明を利用するのが一般的です。
これにより、相手に確実に届いた事実とその内容を郵便局が証明してくれます。トラブルが裁判に発展した場合、この送付記録が有力な証拠となり、あなたの主張を裏付ける材料となります。
注意点4:債権が時効に近づいていないか確認する
金銭債権には時効があります。たとえば、個人間の貸金は原則として10年で時効にかかりますが、商取引などでは5年など、場合によって異なります。
時効が近づいている場合、催告書を送ることで一時的に時効を中断することも可能ですが、手続きには慎重さが求められます。できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
注意点5:弁護士や行政書士に相談すべきケース
催告書を出すことで状況が悪化するケースもあります。たとえば相手が逆上してしまったり、書面の不備を突いて開き直ったりすることも。
また、高額なトラブルや法人相手の場合には、法的な根拠を踏まえた文言が必要となることが多いため、最初から専門家に相談することが安心です。
まとめ:催告書は冷静かつ慎重に
金銭トラブルは誰にでも起こり得るものです。しかし、感情的に対応してしまうと、かえって問題がこじれてしまうリスクも。
催告書を出す際は、冷静に事実を整理し、相手に誤解なく伝わるよう文章を構成することが重要です。そして何より、トラブルが深刻化する前に、行政書士など専門家の力を借りてスムーズな解決を図ることが大切です。
行政書士しまだ法務事務所では、内容証明の文書作成から郵送の流れまで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。